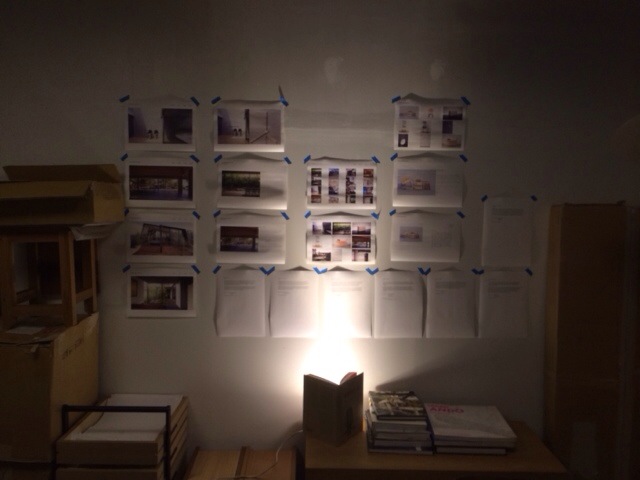なぜ特注照明を作るのか
今から15年前の話。今はトップ照明デザイナーである岡安氏がまだ独立する前に彼とプロジェクトを行い、光を自由に作れるということに衝撃を受けた。それは理想の光を作ること、そしてそれを形にするというプロダクトの意味においてもその自由度と可能性に感動したのである。あれから15年たち、今もなお僕ももちろん岡安さんも光を作りつづけている。
実は光をコントロールすることは大変難しい。照明デザイナーという存在がいることもうなづける。がしかし、出来ればアーキテクトがコントロールするに越したことはない。構造、空間を完全に把握することがまずは大変重要だからだ。光は形ではない。拡がる粒子と捉えるのが正しい。しかしながらこの概念は、繰り返し光について考察、体験をという訓練によって手に入れられるものだ。僕自身20年近く携わってきてもなお難しさを感じるくらいだし、事務所でも何度となく図面での検討が繰り返され、最後は現場で微調整が行われる。
同時に光の多くがプロダクトデザインであることも大変悩ましい問題である。既製品のプロダクトは最大公約数で作られており、まさか出来上がる空間に配慮されてはいない。巨大なテレビがリビングについて考えられていないように、(リビングに置かれた巨大なテレビはまるでテレビの広告のよう。。)往々にしてカタログから選んだ照明器具は空間を不思議な世界へと誘っていく。これは困った問題だが、通常照明器具はあの分厚いカタログから選び、小さなデテールに目をつぶり渋々そこに置くことになる。
しかしながらかつての名建築をみると、そうした借り物はなにひとつない。いや、あるかもしれないがまず目にはつかない。アーキテクトはそこまでやって始めて空間の能力を引き出すのだ。逆にそこで作った照明を商品開発していくアーキテクトもいる。レンゾピアノで多く使われる器具はいま
http://www.iguzzini.com
から発表されている。彼らが作る空間との相性は抜群である。が、僕が使うには少しデテールが特徴的すぎる。いずれにしても、彼らはその照明を多くの建築に繰り返し使っている。
僕が携わる建築においても、照明のデザイン、光のあり方、出てきてしまう形に細心の注意を払うわけだけど、必ずしもその予算が確保できるわけでも、そこまでの時間やテストが確保できないことも多い。その場合の既製品の照明を使いこなす手法はゼロではないが、よく目につく器具はできれば建築のあり方に配慮されたものをデザインしたいと思っている。
こうした考え方は、おそらく建築家が長い歴史の中で受け継いできたレシピのようなものである。先日紹介したBawaや僕の先生であるPeterの建築でも光の扱いは繊細だ。僕がPeterから多くを学んだWall Houseでは既製品の照明は一つもない。ダウンライトですら使っていない。全て岡安氏と製作した。写真からわかる話ではないが、実際にいくと空間が見事に調和していることに感動する。プロポーションや材料の力は大きいが、小さなデテールまでのデザインが重要であることを僕は受け継いでいきたいと思っている。
写真はwall house
Ishinomki Laboratry – cat
Custom Lighting – 特注照明
OFFICE
Our office is in ground level and open to the road.
In spring and autumn,we just open the door and enjoy hearing the noise and chatting of students.
Someone often see our activities and models through the windows and they misunderstand the book store instead of design office.
We renovated this space from umbrella shop that owner organized sevral years ago.
We spend more money to replace windows and doors.
Photo is our entrance door.
Architizer
We are happy to announce Architizer choose our projects as Project of the day.
House S 31/01/2014
2 courts house 02/02/2014
Design small things
We could learn a lot from his detail.http://www.geoffreybawa.com/
My friend took photo handle and lighting in bedside.
You can see the similarity.Such details make beautiful rhythm in space.
I remember this is one of the important idea that I leaned from Peter Stutchbury.
We should try thinking any detail and making by ourselves.
Otherwise,it’s difficult to make beautiful rhythm,one of the most important thing in architecture.
上棟式/Cerebration
Cerebration for Finishing Structure.
It’s topical ceremony that client invite carpenters and us.
最近大工さんはお酒を飲まないので(車で来ているから)割とおとなしい会となることが多いです。
Job offer
We are looking for Architect who speak Chinese and English or Chinese and 日本語.
Just mail us your CV and portfolio.
info@keijidesign.com
Thanks.
Keiji Ashizawa
News
“House S” are featured as “Architecture of the day” of architizer
Architizer というwebのメディアで、 “Architecture of the day” をいただきました
New Projects in our website
いくつかの新しいプロジェクトです。
Furniture
IE shelf
KOBO BENCH
KOBO SOFA
Ishinomaki Bench
Ishinomaki Stool
Ishinomaki High Stool
Arhictecture
WINE APARTMENT
SPACE9 APARTMENT
Interior
Ao Studio :renovation
701 :renovation
Lingting
Glass Parabola
ELLIPSE
石巻工房
石巻工房を会社化することになった。立ち上げてから2年半。販売を始めてから2年がたつ。(ここまでは石巻工房工房長の個人事業である。)石巻でのメンバーは6人。4人が石巻に住み、2人が仙台から通っている。今も多くのサポートを東京のデザイナーから受けているけれど、今年会社化をすると共に完全な自立を目指している。
すでに石巻チームにおける給与や2つの倉庫、オフィス、そして工房などの家賃はなんとか回してきた。現地雇用もそうだが、現地不動産を活用することが石巻工房の一つの役割だった。現在5つの場所を借りてすこしずつお金を落としている。ひとまずそのアイデアと思いは達成したと言えるだろう。ワークショップの大家さんからは、石巻工房ストリートにしたらいいと応援されている。僕もチームも本気でそうしたいと思っている。
どこまで大きくするかは、家具メーカーにおいては必ずしも思惑通りにはいかない。ちょっとずつ背伸びしながら成長を促す他ない。その小さな背伸びにおいて、特にいま力を入れているのが海外進出とコントラクト業務である。海外へは去年2度、今年はまずアンビエンテに出品する。ケルンにもaa stoolのみ出品した。海外からのメディア対応も増えつつある。海外進出は単なるブランドということではなく、本気でビジネスをする作戦でいる。それなりに柱として計算できるところまで来ている。コントラクトに関しては、徐々に増えている。簡単に、そしてそれなりに安価でかつデザイン、コンセプトがしっかりした家具は実のところそんなにあるものではない。また既成材料だけを使ったザックリな家具がもつ力強さ、アイデアは石巻工房ならではと言える。ここには家具のデザインとしても、インテリアをつくっていく上でも大きな可能性をひめていると思う。
そんなコントラクトに関してだが、いままでどのような工事を石巻工房でおこなってきたかまとめてもらった。
これらの仕事をみて、安心して石巻工房に仕事を頼んでもらいたいし、可能性も知ってもらいたい。
そして石巻周辺でも暗躍して、工房ストリートのみならず地方都市の可能性をデザインから生み出すことも続けていけたらいいと思っている。